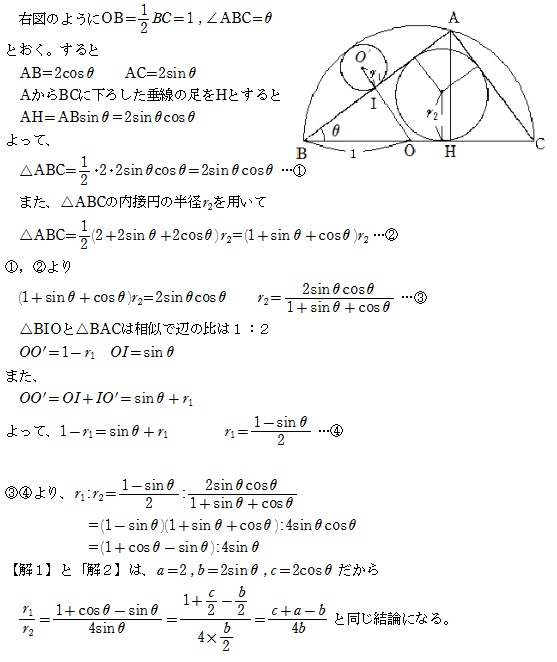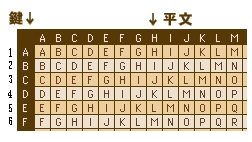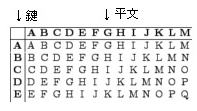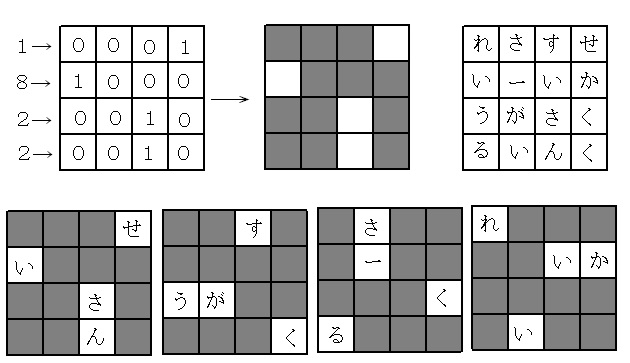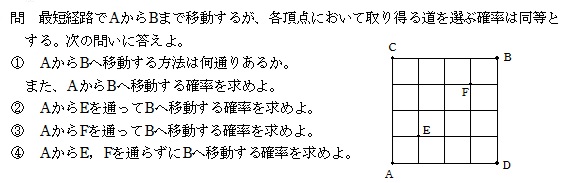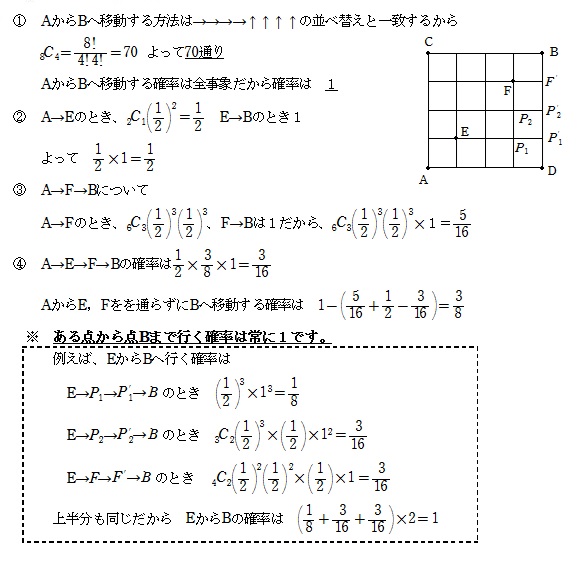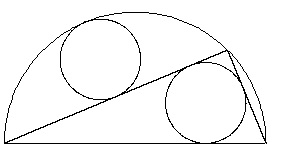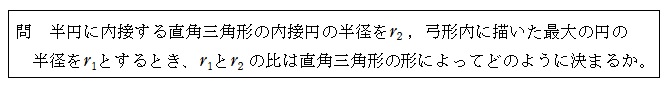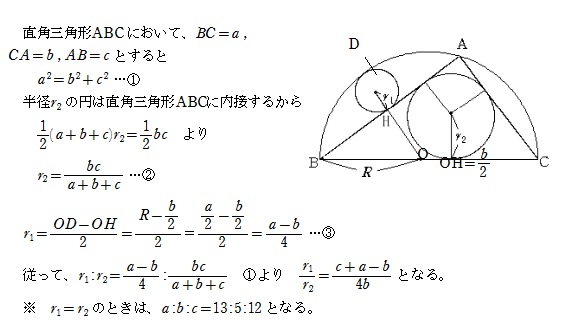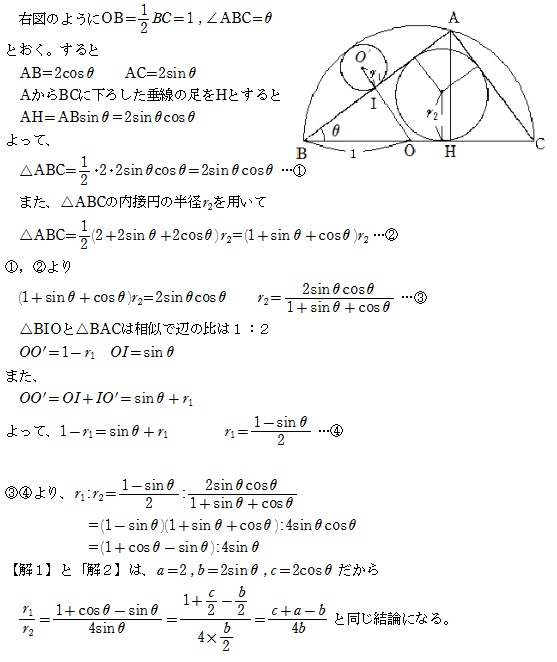西三数学サークル通信136号
暗号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・竹中
① シーザー暗号
平文(暗号化されていないデータのことを平(ひら)文(ぶん)といます。)の各文字を辞書順に3文字だけシフトして暗号文をつくる暗号です。
このシフト数は,3に限る必要はなく数を3以外にした方式も可能です。これをシフト暗号と呼びます(これも広義のシーザー暗号と呼ぶことも
あります)。古代ローマの将軍ガイウス・ユリウス・カエサル(英語読みでジュリアス・シーザーB.C.102-B.C.44)が初めて使ったことから、この
名称がつきました。
例 平文:BAG→暗号文:EDG(3文字だけシフト)
平文:IBM→暗号文:HAL(-1文字だけシフト)
② トリテミウスの多表式暗号
ドイツの修道僧ヨハネス・トリテミウス(1462~1516)は、晩年に暗号解読
の研究を行い、独自の多表式暗号を考案しました。この暗号では、1行目
はAからはじまるアルファベットを、2行目はBから、3行目はCからと1文字
ずつずらして記入した26行の表を作成します。もとのメッセージの1文字目
は1行目、2文字目は2行目という具合に、ひと文字毎に1行ずらした行を使
って暗号化していき、27文字目以降はまた1行目から使っていきます。
例 平文:BAG→暗号文:BBI(最初の文字「B」は1行目の表を使って「B」
に、2文字目の「A」は2行目を使い「B」に、3文字目の「G」は「I」に変換) |
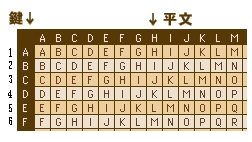 |
③ヴィジュネル暗号
フランスの外交官、ブレーズ・ド・ヴィジュネル(1523~1596)は、トリテミ
ウスの多表式暗号に"鍵"となる文字を使って変換する、強力な暗号を考
案しました。
この暗号は、鍵によって全く異なった暗号文ができあがるので、万が一
換字表が敵の手に渡ってしまっても、鍵が分からなければ解読は非常に
困難になります。
例 鍵:BBCとする。平文:BAG→暗号文:CBI(最初の文字は鍵のBと平
文のBからC,2番目の文字は鍵のBと平文のAからB, 3番目の文字は鍵
のCと平文のGからI) |
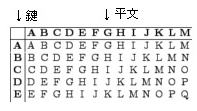 |
① 転置式暗号(回転グリル方式)
正方形の升目の板(グリル)の、一見でたらめな位置に孔(あな)を開け、そこから下の紙に文字を書き込んでいきます。
すべての孔に書き込んだら、グリルを90度回転して続きを書きます。これを4回行ってすべての升目の位置を文字で埋めま
す。この方式はオーストリアの陸軍大佐フリーシュナーが1881年に考案したものです。
例 右図の4×4のマスに16文字が入っています。この文字を並べ替えると、1つの言葉になります。
暗号を解くキーナンバーは1822です。
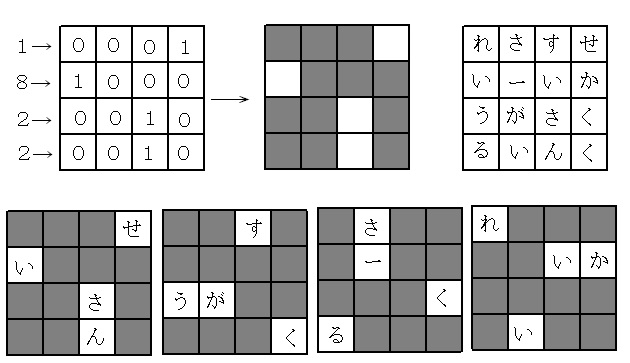
最短経路の確率の問題・・・・・・・・・・・・・・・鈴木
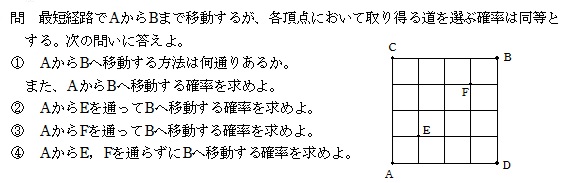
【解答】
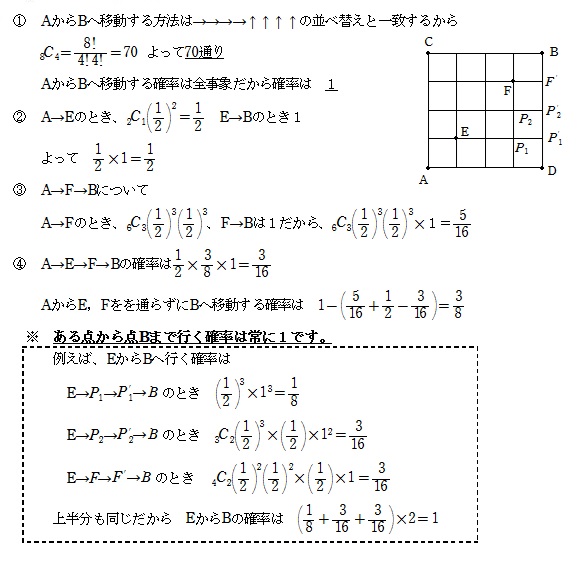
算法少女
|
小説「算法少女」(遠藤寛子・ちくま学芸文庫】は、
下図のような算額問題の誤答から話が始まります。
問題文 「半円に直角三角形を内接させ、この
直角三角形の内接円と弓形内に描いた最大の円
が等しいとき、半円の半径と小円の半径の比を求めよ。」
誤答=3:1 , 正答=13:4
|
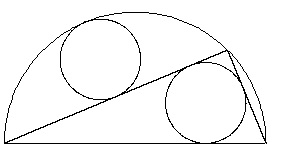 |
この問題の次のような一般化が例会で話題になりました。
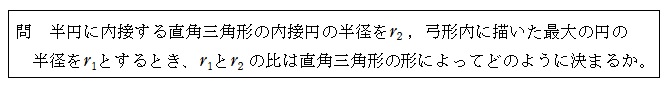
【解1】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤
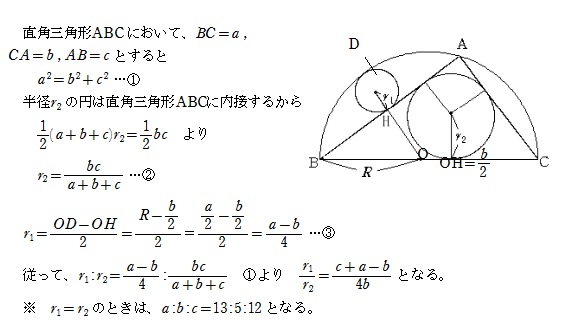
【解2】・・・・・・・・・・・・・・・・・山内